|
僕と君の物語
第一話『僕と新学期』
第二話『僕と隣人と居候』
第三話『僕と雨宮と父の電話』
第四話『僕とかえでと休みの日』
第五話『僕と登校と月曜日』
第六話『僕と夜と旅行計画』
第七話『』
メニューへ戻る |
|
アルセリア様のオリジナル小説です。 帝國に出していただいた小説では第二弾。 相変わらず素敵な小説を作って頂いて本当に嬉しく思います。
帝國史書係 セイチャル・マクファロス
文・絵/アルセリア様  *1 / *2 / *3 / *4 |
|
*1 ▲ 夢を見ていた。 それは、昔の僕の夢。 僕は今、僕自身を俯瞰して見ている。 積み重ねた本に囲まれて、僕は本を読んでいる。 これは、いつのころの僕だろうか。 『入るぞー』 そんな声と同時に、部屋のドアが開いた。 父さんが、満面の笑みとともに部屋に入ってくる。 『…何?』 子供の僕が、とても嫌そうな顔で父さんの顔を見上げていた。 …ああ、わかった、これは7歳の頃の僕だ。 そしてこのあとに起こることも、僕はわかってしまった。 あの珍妙にして全力で馬鹿げている事態が起こるのだ。 『なあ、聡介』 『血の繋がらない妹は欲しくないか?』 『…どうしよう、お父さんの頭がおかしくなった』 『いや、お父さんは正常だぞ』 いや、あれから10年近くたった今でもあんたはおかしいと思ってる。 真性のアホだ。 『やはり主人公には義理の妹が必要だろう』 『お父さん、ほんとその教育方針止めようよ。受けてる側にとっては結構切実なんだよ』 そう、この親は僕を『主人公』に育てようとする異常人物なのだ。 そしてその教育方針は、現在に至っても続いている。 『何を言うんだ。主人公はいいぞ、なんといってもモテモテだ。ハーレムエンドすら視野にいれることができる』 『視野に入れてる時点で誠実さのかけらもないよね。ただの下種野郎だよね』 『なぁに、全員を本気で愛することによってプレイヤーにも愛される主人公を育てることが俺の目標だ』 『僕にはプレイヤーがいるんだね。というか多分お父さんがやってる育成ゲームの主人公だよね、多分』 『違うな、今はまだキャラクターメイキング中なんだ、おまえの初期値はまだ定まっていないよ』 『僕の人生は始まってもいなかったんだね』 『子供時代の行動がキャラメイクというゲームも存在する。おまえは正にそれさ』 それは何のフォローになっているのだろうか。 『こんなにも父親のゲーム脳に巻き込まれた人って、多分世界中を探しても、他にいないだろうね』 しかもギャルゲー脳だ。 救いようもない。 『オンリーワンだな』 『わあ、全く嬉しくないや』 『おまえが7歳ながら女の子の友達を複数作ってるのも主人公らしいと言えるな』 『…』 7歳の僕が父さんに本を投げつける。 同時に走りだし、跳躍。 父さんの顔を狙って、とび蹴りを放っていた。 …受け止められたけれど。 『お父さん、流石にその発言はむかつくよ』 『ふっ、それでいい。それでこそ主人公だ』 とび蹴りをした際に捕まれた足が放される。 『…もういいよ』 と、言いながら、7歳の僕は父さんに背を向けた。 その直後、更に振り向き、パンチを父さんの腿に向けて放つ。 …また、受け止められた。 『まだまだだな。今のおまえじゃあ父さんに攻撃を当てることはできん』 『…だからもっと鍛えろって? 父さんってそればっかだよね』 そう、そればっかりだった。 大した工夫もなく、そんなことで僕を煽って。 そして僕は、 『…今にみてろ』 いつもいつも、それに乗っていた。 …僕も馬鹿なのだろうか。 少し凹んできた。 『うんうん、それでいい。で、話を戻すがな…』 『…ああ、義理の妹だっけ? いらないよ、そんなの』 『もう連れてきている』 『…』 7歳の僕は膝から崩れ落ちた。 両手を地につけたその姿には哀愁がただよっている。 『…連れて、きたんだ』 『ああ、おまえの1つ下で美少女に育つであろう資質を持つ女の子を見つけるのは大変だったぞ』 『とうとう他人まで巻き込みだしたよこの父親!!』 7歳の僕は失意体前屈の体勢で叫ぶ。 『他人ではないぞ、もう家族だ!』 『いいこと言ってるつもりか! お母さんはなんて言ってるのさ!?』 『うむ、母さんは「あらあら、それじゃあ娘ができるのね。楽しみだわー」と言っていた』 『器が大きすぎる!!』 『ああ、あの母さんだからこそ、おまえを主人公に育てることすら許されるんだ』 『畜生! 最悪のタッグだ!!』 まともな両親が欲しい。 このままでは僕の新しい家族の人生すら危うい。 『…何、じゃあ、今はどこにいるのさ、その子』 『ああ、ドアの外で待たせてある』 『主人公云々とか全部聞こえてんじゃん!?』 『家族間の隠し事はよくないからな』 『隠してたよね!? 養子探してたの隠してたよね!!』 『すまない、言うのが遅れたな』 『かなりやばいレベルで遅れたね!!』 『よし、それじゃあ入ってきなさい!!』 父さんが、部屋のドアに向かって、その外にいるであろう義妹に向かって声をかける。 そして、ドアがゆっくりと開きだす。 一人の小さな女の子が、顔を出す…。 『紹介しよう、この子がおまえの新しい妹、朽木家の新しい家族、海だ!!』 そこで、夢から覚めた。 |
|
*2 ▲ 僕と君の物語 第一話『僕と新学期』 ピピピピピ ピピピピピ ピピピピピピピピピピピ そんな、目覚ましの音と共に僕は目を覚ました。 なんだろう、酷く疲れている。 酷く疲れる夢を見たからだろうか。 特に二度寝することもなく、ベッドから起き上がる。 手で適当に寝癖を直しつつ、部屋を出る。 我が家は階段を下るとすぐのところに食卓がある。 そこでは母さんが朝食を用意していた。 今日の朝食は和食のようだ。 …ちなみに父さんは、『主人公の家にお父さんが一緒に住んでいたら邪魔だろう』という謎の理由で単身赴任中だ。実に馬鹿だと思う。 まぁそのおかげで、ここ最近はのびのびと暮らしているのだけれども。 「母さん、おはよう」 「あらおはよう。もうすぐ朝ごはんの用意ができるわよー」 「食器、並べようか?」 「こっちは大丈夫よ、それより海を起こしてきてくれる?」 「遠慮します」 「お願いするわねー」 聞いちゃいねぇ。 「…はぁ」 仕方がないので今度は階段を上りだす。 海の部屋は、僕の部屋の隣にある。 子供の頃、何故この部屋が物置にすら使われていなかったのか少し疑問だったのだけれど、どうやらこれを狙ってのことだったらしい。 あの父親は、いつから養子をとるつもりでいたんだろうか。 こんこん 僕は海の部屋のドアをノックする。 返事はない。 「おい、起きてるかー?」 やはり返事はない。まだ寝ているんだろうか。 そんなに朝が弱いタイプでもなかったはずだが。 「おーきーてーるーかー?」 …。 「くそっ、入るぞ、入るからな?」 また5秒程待ってみたが、やはり返事はない。 僕はドアノブに手をかけた。 何か嫌な予感を感じつつもドアノブをひねり、ドアを開けていった。 部屋の中の様子が目に入る。 「きゃー」 「…」 着替え中だった。 下着姿だった。 「妹の着替え中にドアを開けて侵入してくるとは、とんだエロス溢れる兄ですね」 「返事を一切しない馬鹿妹が原因じゃねーかなーと僕は思う」 おまえ、あれだけ返事待ってその姿なあたり、下着姿で待機してたろう。 露出狂か貴様は。 「誘惑されましたか?」 「誘惑されないな、僕は妹に欲情するような男じゃない」 「ああ、そういえば兄さんは下着丸見えよりパンチラに興奮するタイプの人でしたね」 「兄の話を聞くんだ。僕は妹に欲情しないと言ったんだぞ」 それが事実かどうかは横に置いておく。 「では、もし私が兄さんのクラスメイトの下着をつけていたらどうなりますか?」 「僕は妹の下着に欲情しないと言ったのではなく、妹に欲情しないと言ったんだ」 「ほぅ、でしたらもし私が姉だったとしたらどうです?」 「言い換えよう。僕は家族に欲情しない」 「つまりゲイですね」 「家族に欲情しなければゲイだと言うのかおまえは」 「世界共通の常識ですね」 「滅びてしまえそんな世界」 というか間違いなく人類は滅びる。 「まぁ、とりあえずおまえが起きてるのはわかった。僕は飯を食ってくる」 「待ってください兄さん。ここで私のブラのホックを兄さんが止めてみるというのはどうでしょう」 「もうノーブラでいいよおまえ」 僕はドアを閉める。 階段を下りて食卓へ。 朝食の準備はできていた。 「海は?」 「起きてた、多分もうすぐ来る」 「あらそう、ご苦労様」 「いえいえ。んじゃいただきます」 僕は手を合わせた。 僕が朝食を半分程平らげたころ、海が階段を下りてきた。 すでに制服姿だ。  朽木 海 「おはようございますお母さん」 「おはよう海」 挨拶をしつつ、食卓に座る。 よく見ると、なにやら海が胸元を摘んでいた。 何をしているのか。 「あら、どうかしたの、海?」 「兄さんにノーブラを強要されました」 僕は味噌汁を噴き出した。 僕のシャケが味噌汁まみれになった。 メインを最後に残す僕の食べ方が、裏目に出てしまったのである。 「あらまぁ、困ったわねぇ」 「ええ、困りました」 「困らない! もう一回部屋に戻ってつけてこい馬鹿が!!」 「兄さん、エスコートしていただけますか?」 「さっさとこいやおらぁ!!」 僕は海の腕を強引にひっぱり、階段を上っていく。 そして海を部屋にぶちこんだ。 即座にドアを閉める。 「とっとと下着つけて飯食いに来い!」 「下着のカラーはどうしますか?」 「しらねぇよ!」 「ええとですね。私の持っている下着の種類は…」 「違う、僕はおまえの持っている下着の種類を知らないと言ったんじゃない!」 「既に知っていましたか、流石は兄さん」 「そういう意味でもないわ! てか流石ってどういう意味だ! とにかく早くしやがれ!」 僕はドア越しに叫び、その場を立ち去った。 再度僕は階段を下る。 僕は今朝のうちに何度この昇降運動を繰り返すのだろう。 …ああ、制服着なきゃいけないから最低あと一回か。 そして僕は、再度食卓についた。 「くそっ、新学期早々遅刻寸前だと!!」 「私なぞ高校生活で最初の授業のある日ですからね」 「おまえのせいだから! 遅刻しかけてるのおまえのせいだから!!」 そう、今日は僕にとっても、二年生としての授業最初の日なのである。 入学式、始業式等は終了済みだ。 だがだからといって、新しいクラスメイトとろくに顔合わせもしていないのだ。 このまま遅刻してしまっては、クラスメイトにどんなイメージを刷り込んでしまうかわかったもんじゃない。 そのため、僕達は今全力疾走中だ。 「私達、陸上部に入ればそこそこなとこまでいけそうですよね」 「しゃべりながら走ってるあたりな!」 父さんにやたらと鍛えられた結果がこれである。 どうやら父さんは、主人公はハイスペックであるべきという考え方を持っているようなのだ。 子供の頃の僕が本に囲まれていたのも、その一環だった。 本を読むのは好きな方だが、あの物量はおかしかったと思う。 ついでに海も僕にくっついて一緒に色々鍛えた結果、かなりのハイスペック女と化してしまっている。 どんな兄妹だ。 「残り時間は!?」 「あと8分あります。少しペースを落としても大丈夫そうですね」 「…あー、まぁ学校ついて汗だくってのもあれか」 それはそれで、与える印象は悪そうだ。 僕は走るペースを落とし始める。 学校には、あと5分程度でつくだろう。 「…んぉ?」 僕らが走る通学路、その先に座りこんでいる人を見つけた。 …と、思ったらずるずると倒れた。 「…うわぁ」 「倒れましたね」 僕らはその倒れた人物の前で立ち止まった。 服装を見るに、女生徒である。 コンクリの道に女子高生が倒れている姿は実にシュールだった。 「あの…大丈夫ですか」 僕は声をかけてみる。 何かの急な発作だったりしたら大変である。 「日光が…日光がつらい…」 すると、久々に外にでた引きこもりのような答えが返ってきた。 「どうしよう妹よ。駄目な人だった」 「いえ、兄さん。この方は勇気を出してようやく外に出ることができたのかもしれません」 「そうか、それは素晴らしいな。でもどうしよう」 「兄さんがおぶって走るというのはいかがでしょう」 …妹よ、人を背負った状態で走り続け、遅刻せずに辿りつけとでも言うのかい? 「そのとおりです」 「鬼か貴様」 鬼のような妹が、そこにはいた。 「…君、学年は?」 「…二年生ですねー」 僕と同学年だった。 「頑張れ兄さん」 「頑張れ僕!!」 僕は頑張った。 |
|
*3 ▲ キーンコーンカーンコーン 「間に合ったぁ!!」 僕はチャイムが鳴ると同時に教室のドアを開けた。 そして僕に向くクラス中の目線。 奇異なものを見る目が、僕を見つめている。 「…うん?」 なんだ? 確かに遅刻寸前で駆け込んだが、そんな目で見ることは…。 「…うぅ、酔いました…」 「…」 僕は奇異なものを背負っていた。 「いや、違うんだ」 何が違うというのか。 焦っていたからといってそのまま教室に駆けこんでどうする、僕。 階段がやけにしんどかった時点で気づけ僕。 「…おい、そこの背中の奴」 「…何です?」 「…おまえ、クラスは?」 「…二の二ですねー」 ここだった。 なんとクラスメイトである。 「おい、こいつの席はどこだ!」 「おぉっ!?」 僕は近くに座っていただけの善良そうな男子生徒に詰め寄った。 今の僕は必死だ。 一刻も早く、これを手放したい。 「え、いや、知らねぇよ、そんなの」 「は、全く無知な野郎だ。罰としてこいつを背負うんだな」 僕はその男子生徒に背中の異物を投げ渡した。 外道の所業である。 「ぐぉ、な、なにすんだてめぇ!!」 「見知らぬ女生徒を見知らぬ男子生徒に放り投げた」 「なにしてんのおまえ!?」 実にもっともな意見だと思う。 でもわかってくれ、これは仕方のないことなんだ。 「…いたい」 「…と、おいおいおい、ほんとなんだよ! どうしろってんだよ! なんだこの子!」 「まぁ落ち着けよ竹中」 「誰だよ!?」 「そしてさらばだ竹中」 「まてやぁ!!」 僕はダッシュで自分の席(座席表配布済み)に向かった。 先生が教室に入ってきたのである。 これは急がねばならない。 「おーう、おはよう。元気してるかおまえらー…何してんの、おまえ」 「…なんでしょうね」 先生の目には、竹中がぐったりした女と抱き合う姿が映っていた。 僕は竹中を犠牲に救われたのだ。 キーンコーンカーンコーン 授業の様子はカットされ、昼休みである。 僕は母が作った弁当を鞄の中から取り出した。 『私が作りました。海』という紙が挟んである。 嘘である。 ピシャーン! 教室の戸が凄い勢いで開かれた。 教室中の目線がそちらに向かう。 僕はそこにあった姿を見た瞬間、ドアの方へと走り出した。 「セッンパーイ! 愛しの後輩が今参上しましたよ! 久々に見た愛する後輩の姿はどうですかセンパイ! うっふっふー、見違えたでしょう惚れなおしたでしょう愛は深まったでしょう! さあ! 遠慮せずに抱きしめていいんですよ!!」 ピシャリ 僕はドアを閉めた。 我ながら俊敏な動きだったと思う。 「…おい、今の、なんだ?」 竹中が声をかけてくる。 なんだろうね。 「ああ、珍獣じゃないかな。ほら、珍妙だったろう?」 「いや見た目は可愛かったような」 「女は見た目じゃない、心さ」 「かっけー」 そう言いながらも竹中は呆れた顔をしている。 いや、僕も言っててどうかと思ったが。 「センパイセンパイどうしたんですか? 何故ドアを閉めましたか? あ、わかりました! 私に図星をつかれちゃったからですよね! センパイったら照れ屋さんですねぇ。でもそんなセンパイも大好きですよ! でも顔が見えないのはちょっと寂しいです! ですからこのドアを開けてくださいなセンパイ!」 橘かえでがドアの向こうから何か妄言を吐いている。 この女、悲しいことに僕の中学時代の後輩である。 「…何故、貴様がここにいる」 こいつと僕の学力には、かなりの差があった記憶がある。 というか、僕の進学先を教えた記憶もない。 「先輩を追ってこの学校に入学しました! 偏差値を10は上げましたよ! でもセンパイのことを思えば全然辛くなんてありませんでした! むしろ勉強するほどにセンパイに近づける気がして幸せな心地だったくらいです! 愛の力って凄いですよね!」 「なあ、愛とか言ってるぞ」 「ああ、哀しいって意味のあいじゃねぇかな」 僕はきっと今、哀しい目をしている。 「もう春休みの間も先輩に会いたくて会いたくて! 家に電話してもいっつも海ちゃんが出てきて「今日兄さんは私と愛を語り合うという用事があるんです」って言うから会えませんでしたし! センパイったらとんだシスコンですよね! ところでたまには私と愛を語り合いませんかセンパイ!」 「…妹と愛を語りあってるのか?」 「殺し合いとかそんなんじゃねぇかなぁ」 僕は今、激しく妹を殺したい。 主に喉を攻撃する方法で殺したい。 「さぁさ、このドアを開けてくださいセンパイ! さもないとこの後もどんどんと周りに聞かれたくないであろう情報を垂れ流しますよ!」 「わざとかてめぇ!!」 僕は怒りと共にドアを開けた。 「セーンパーイ!!」 その瞬間、かえでが両手を広げて突進してきた。 横に避けて足をひっかけてみる。 「うおえあーーっ!!?」 「…おおぅ?」 体勢を立て直そうとして失敗し、一つの机を巻き込んで大転倒。 犠牲となった机に載っていた筆箱がぶちまけられる。 大惨事だった。 机に載っていたのが食べ物ではなかったのが唯一の救いか。 「…どうしてこうなった」 「いやぁ、おまえのせいじゃねぇかなぁ」 「そんなことはないよ竹中」 「俺は鈴木だ」 「ニックネームだ」 「やめれ」 「いやいや…んなこと言ってる場合じゃないでしょーよ、あんたら」 竹中の後ろの席の女生徒が声をかけてきた。 まぁ、確かにそのとおりだ。 僕は惨事の現場に目をやった。 「ふぅ、びっくりしました! びっくりさせてくれますね、センパイったら! もうドキドキです!」 かえでは無傷だった。 何故か笑顔である。 「…あぁ、おばあちゃんが手を振ってます…」 巻き込まれた側は瀕死だった。 ていうか僕が今朝運んできた子が瀕死だった。 よく瀕死になる奴だ。 さて、このまま死んだらこの場合、殺人犯は誰になってしまうのだろうか。 きっとかえでだな。 「やだなぁ、おばあちゃんじゃなくてかえでちゃんですよぅ!」 「…なんだ、かえでちゃんですか」 「そう、私の名前は橘かえでです!」 「ほうほう、私は雨宮鈴音です」  橘 かえで 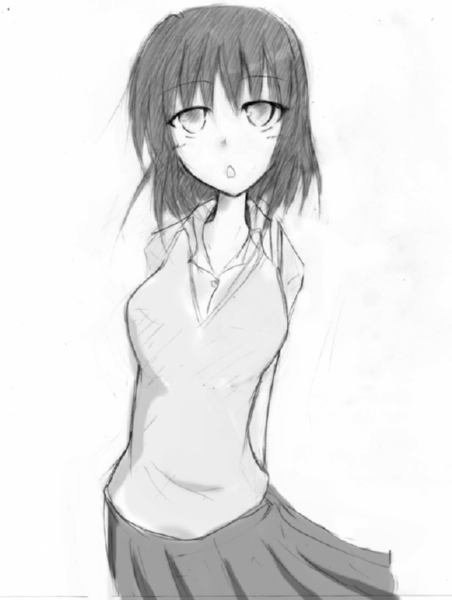 雨宮鈴音 何故か自己紹介がはじまった。 何故だ、僕にはわからない。 「竹中、僕はどこからツッコミをいれればいいんだい?」 「とりあえず俺はおまえに俺は竹中じゃねぇとつっこむよ」 僕は竹中を無視することにした。 「しかしまぁ、虚弱な割に案外復活は早いな雨宮」 「あまみーと呼んでくださっても結構ですよ?」 「いや、別にそんな風に呼びたくはねぇよ」 「あまみーはしぶとさには定評があるのです」 「素敵な定評だな」 ついでに体を丈夫にすべきだと僕は思う。 というかおまえ、一人称あまみーでいくつもりなのか。 「いいなーあまみー先輩! センパイに褒められるだなんて羨ましいです! 私も素敵とかセンパイに言われてみたいんですけど、そこんとこどうでしょうセンパイ!」 「素で敵だよなおまえって」 「“で”がいらないですよーぅ!!」 「ところで、怪我はないか雨宮」 僕は転倒して今だ床に座っている雨宮に目をやった。 ぼーっとしてるから、痛いところがあるんだかないんだか、さっぱりなのである。 「あ、無視だ、センパイが私を無視ですよ! センパイってば久々に会う後輩に対してなんて仕打ち! でも大丈夫! これも放置プレイの一環だと考えればほらこんなに幸せな気持ちに! きゃあセンパイったらいやらしいですね!」 「レベルたけぇなぁ、おい」 竹中が口をはさむ。 待ってくれ竹中、僕はそんなプレイに興じるマニアックな人間じゃあないんだ。 単にこいつが変態なんだ。 「…ほほぅなるほど、あなたは変態さんだったのですね。それでは私を背負って学校に運ぶという善行を行うと同時に、お尻の感触とかを楽しんでいたりしたんでしょうか。エロスに溢れていますねぇ。ははは、こやつめ。あ、怪我はありませんのでご心配なくー」 「おまえのキャラが掴めねぇよ雨宮」 何キャラだよ。 虚弱毒舌のんびり天然キャラなのか。 どんな層を狙っているんだろう。 「ところでセンパイさん」 「僕はおまえのセンパイではねぇよ」 「いえ、それはわかっているのですがお名前はなんというのですかー?」 …ああ。 言ってなかったっけ。 「朽木聡介だ」 「なるほど、言われてみればあなたから朽ち果てた木のような雰囲気を感じますねぇ」 「首を絞めてもいいかな、雨宮」 「いえいえ、そんなことをすれば私の虚弱っぷりからして、即死しますよ?」 即死するのか。 それは困る。 僕は前科をもらいたくはないのだ。 「くっ、案外厄介な体質だな」 「ええ、主に本人にとって厄介な体質なんです」 そう思うなら体を鍛えてみてはどうだろうか。 そうすれば、僕も心置きなく首が絞められる。 「それはできませんねー」 「地の文を読むな」 「私は体を鍛える気はありませんよ」 「なんだい、何か理由でもあるのかい?」 「面倒ですからー」 「おまえは本当に駄目な奴だな」 そうか、虚弱毒舌のんびり天然無気力キャラなのか…。 なんだろう、駄目かわいいとかそういう路線なんだろうか。 憎めない奴ではあるのだが…。 「それにしてもセンパイ、もしこの場に海ちゃんがきたら大変ですね」 「は? いや、まぁ、心の底から大変に決まってるじゃねぇか収集つかねぇよ馬鹿野郎と思うが、何故そう思った?」 「ですます調の人が多いので判別がつきづらいじゃないですか!」 「おまえは何を言っているんだ」 「個性を前に出していかないと埋もれてしまいますよ!」 「おまえは何を言っているんだ」 なんだろう、こいつは上位世界からの目線で物を見ているんだろうか。 とりあえずおまえの個性はあれだな、元気。 「ここは変わった口調の人も登場すべきかもしれません!」 「おまえ、この状況を更にカオスへと叩き込みたいのか」 「語尾にニャと付ける人とか!」 「それはただの痛い人だな」 「案外いません!」 「いたら逃げるわ」 「私はあまみーですにゃー」 「死ねばいいのに」 僕は、逃げはしなかったが酷い事を口走っていた。 もはや僕の中で、雨宮に対する遠慮というものが消え失せつつあった。 なんだろう、今日初めて会ったはずなんだが…。 「死にません。私は『あまみーっていつも死にそうな割に案外死なないよねー』と友達にいつも言われていますから」 「それは本当に友達なのか?」 「友達です。私が友達ですよねと尋ねると『え、あー…うん、そうだね』と言っていましたからー」 「いい笑顔を浮かべてそうだな」 苦笑いという名の。 そしてわかった。きっとそれは友達じゃない。 「あまみー先輩とお友達になりたいです!」 「かえでちゃん、ここはいっそのこと親友になりませんか?」 「いいですね! なりましょう」 こうして彼女達は親友になったのだった。 なんだろう、すげぇ軽い言葉に思えてきたな、親友…。 いや、実は僕には親友とかいないんだけど。 …いや、友達がいないわけじゃないよ? 「ところで友達の少ないセンパイ!」 「僕は人生において女を殴っていい瞬間というものがあると思うんだ」 「話はかわるんですけども」 話を変えられてしまった。 話題が変わってしまってはもう殴れない。残念無念である。 僕がそう思っていると、少し離れたところに落ちていた布に包まれた箱を、かえでは持ち上げた。 「お昼、ご一緒してもよろしいですか!」 …ああ、そういえば昼休みだったね。 そして、結局は竹中まで交えての昼食をとることになった。 その際、一度床を転がることとなったかえでの弁当の見た目が愉快なことになっていたり、米を喉につめて死にそうになるというおばあちゃんのような所業を見せ付けた雨宮がいたり、 自分が何故このグループと一緒に飯を食っているのかということに結構な質量の疑問を抱いている竹中がいたり、 なんだかんだで楽しみながら昼食をとっている僕の姿が、そこにはあった。 高校二年生、最初の昼休みだった。 |
|
*4 ▲ 「へぇ、そんなことがあったんですね」 「ああ、結構疲れたよ」 放課後、僕は妹と肩を並べて帰宅していた。 僕は帰宅部で、妹もどこかの部に所属する気はないようだった。 放課後、僕と一緒にいられる時間が減るという理由で部活に入らなかった中学時代を見てきた僕としては、高校ではなんとしても、どこかの部に放り込みたいところなのだけれど。 「私も兄さんの教室へ行けばよかったですね」 「やめとけ、本気で収集がつかん」 「そうかもしれませんね」 「それに、ろくなことにならない、かもしれない」 「…そうかもしれませんね」 大丈夫だとは、思う。 一年間あの高校で過ごしてきた僕は、大丈夫だろうとは感じていた。 でも、中学時代。 ろくなことにならなかったことが、あった。 中学入学と同時に、海は僕の教室に遊びにきて、 ろくなことに、ならなかった。 「兄さん、悲愴な顔をしていますよ」 「ほぅ、この僕がそんなシリアス顔をしていたというのかい?」 「悲惨な顔をしていました」 「それはちょっと意味が違わないか?」 「目を背けたくなる醜さです」 「どれだけ顔が崩れていたんだ、僕は」 「まるで単に不細工な人のようでした」 「おまえ、僕が何を言われても傷つかないとか思ってないか?」 その一言は普通に傷つくのだが。 たとえ冗談でも傷つくタイプの発言だ。 「嘘です。兄さんはかっこいいです」 「…」 それはそれで、反応に困るわけだが。 妹にかっこいいと言われてどうしろというのだ。 「主人公にふさわしきイケメンですね」 「やめろ、その評価は全く嬉しくないぞ」 そして家の外でそういった発言はやめろ。 頭がおかしい人と思われる。 「そして私がヒロインなのです」 「父さんの発言をなぞるな。そういった発言は僕の好感度が危ないんだ」 もしそういうキャラだという目で見られたら、悲惨なことになる。 「は? 兄さんに好感を持っている人なんて私とお母さんぐらいじゃないですか」 「僕の心をどこまで傷つける気なんだ、おまえは」 「そしていつか私だけになります」 「母さんをどうする気だ、貴様!?」 「お母さんは寿命で死にます」 「その時点で僕は誰にも愛されていないというのか!?」 悲惨な人生である。 どれだけ悲惨なんだ、僕。 「娘には『お父さんなんて嫌い』と言われています」 「…ああ、子供はできるんだね」 「私の子でもあります」 「ねぇよ! 僕の娘はおまえの子ではねぇよ!」 「え? 私以外の誰の子だと言うのです?」 「知らねぇよ! でもおまえではねぇよ!」 「でも兄さんに恋人なんてできませんよ?」 「断言しやがった…」 いや、確かに彼女ができたことなど一度もないのだけれど。 可能性まで否定したくない…。 「…大丈夫さ。僕を愛してくれる人が、きっといつかは見つかるはずさ」 「へぇ、例えば?」 「いや、例えばって…」 「セーンーパーイー!」 僕らの後方から、一人の後輩が全力疾走してくる。 「…あれですか?」 「…いや、あれはどうかなぁ」 何を考えているのかさっぱりわからねぇんだもの、あれ。 感じるのは好感ではなく、押し寄せる疲労成分なんだもの。 「つか『あれ』って…おまえの友達でもあるんじゃなかったか?」 「私に友達なんていません」 「作れよ!」 色々な意味で心配な妹だった。 こいつは本当に、まともな人生を歩けるんだろうか。 既にはずれかけている気はするけれど。 「まぁ、向こうは私を友達だと思っていそうですが」 「…ああ、まぁ初めて会った学校の先輩を親友と呼ぶ奴だしな」 「厄介です。このままでは私に友達ができてしまいます」 「何故友達を作るのを嫌がっているんだ、おまえは…」 …でも、友達ができそうとは考えているのか。 じゃ、あいつを嫌ってるわけではないんだな。 「…兄さんが優しい目をしています。非常にうざいです」 「兄にうざいとか言うなよ!」 「さあ、更にうざい人がこっちに来ますよ」 「センパイ! 海ちゃん! 途中まで一緒に帰りましょー!」 妹曰く兄よりうざい人が、息を切らせて、それでも満面の笑みで、そんなことを言った。 「嫌だ」 「嫌です」 「今ダブルで拒否されましたか!? くっ、でも私は挫けませんよ!!」 しばらく会わなかったうざい後輩は、相変わらず元気いっぱいで、 また、僕達兄妹を楽しませてくれそうだった。 |
|
▲ メニューへ戻る 第二話『僕と隣人と居候』へ→ |